1. あらすじ(ネタバレあり)
第13回ガンダムファイトの舞台、ネオエジプトの荒野。ドモン・カッシュとサイ・サイシーはそこで異変を目撃します。今大会のネオエジプト代表機であるはずのファラオガンダムXIII世が何者かに破壊され、整備クルー共々壊滅していたのですg-gundam.net。しかも近くでは、ミイラ男のような包帯に覆われたファラオガンダムIV世がサイ・サイシーのドラゴンガンダムに襲いかかり、激しいガンダムファイトが展開されていました。ファラオガンダムIV世は自己修復能力を備えており、一度はドラゴンガンダムに大破させられてもすぐに再生してみせますg-gundam.netgundam.wiki.cre.jp。サイ・サイシーは苦戦の末、ルール破りと知りつつコックピットへの突き刺し攻撃でファラオガンダムIV世を辛くも行動不能に追い込みましたedgecute.livedoor.blog。ところが翌日、倒したはずの機体は跡形もなく消え失せてしまいますg-gundam.net。
夜、一行は砂漠でキャンプを張ります。月は不気味に赤く染まり、現地の人々が語る「亡霊ファイター」の怪談話にサイ・サイシーは震え上がりますedgecute.livedoor.blog。ドモンは「幽霊だとしても取り憑かれるのはお前だぞ」と冗談めかしつつも、怖がるサイ・サイシーを宥めました(実際ドモン自身も少しは不気味に感じていた様子ですが、素直に怖がらないのがドモンらしいところです)。深夜、どうしても怖さに耐えきれなくなったサイ・サイシーは用を足しにテントを出ますが、そこで再び謎のミイラ男に遭遇してしまいますedgecute.livedoor.blogedgecute.livedoor.blog。
亡霊の正体を探るべく、ドモンたちはかつてネオエジプトの英雄だったダハール・ムハマンドの墓所へと向かいます。ところが墓を開けてみると、中は空っぽ。棺からダハールの遺体が消えていたのですg-gundam.net。その瞬間、棺の奥に飾られたダハールの肖像画の目が不気味に真紅に光り、「うぉ~~~~!」という唸り声と共にミイラ男が襲いかかってきましたedgecute.livedoor.blog。亡霊ファイターの正体はやはりダハール・ムハマンド本人——かつて第4回ガンダムファイトで命を落としたはずの英雄が、包帯だらけの生ける屍となって甦っていたのですw.atwiki.jp。
突然の亡霊の出現にサイ・サイシーは恐怖ですくみ上がります。ドモンはとっさに彼の前に立ちはだかり、「レインを連れて逃げろ!」と指示しますedgecute.livedoor.blog。亡霊ダハールの包帯が生き物のように伸びてサイ・サイシーを締め上げようとする中w.atwiki.jp、ドモンのパートナーであるレイン・ミカムラは手榴弾を取り出し、「アレを使え!」というドモンの合図で投げつけましたedgecute.livedoor.blog。手榴弾の爆発によって墓所内部は崩落し、一行は間一髪で難を逃れます。しかし、直撃を受けたはずの亡霊ファイターはなおも健在でした。崩れ落ちる瓦礫の中から這い出したダハールは、砂中に隠してあったファラオガンダムIV世に乗り込み、再びドモンたちの前に姿を現しますw.atwiki.jp。
ここに至り、サイ・サイシーもついに逃げ腰を返上します。かつて自分の祖父(サイ・フェイロン)が果たせなかった因縁の決着を、孫である自分が受けて立つしかないと悟ったからですw.atwiki.jp。サイ・サイシーは恐怖を振り切り、ドラゴンガンダムに再度搭乗。ミイラ男と化したダハールに真正面からガンダムファイトを挑みます。「よおおおおおし! ガンダムファイトォ…」「レディィ!!」「ゴォーーッ!!!」——サイ・サイシーは自ら公式のファイトコールを叫び、亡霊ファイターもそれに呼応して戦いが再開されましたw.atwiki.jp。戦闘中、レインの調査でダハールの死の真相が伝えられます。ダハールはサイの祖父フェイロンとの戦いで卑怯な手に倒れたのではなく、不慮の事故で命を落としたのであり、怨念というより「戦士として未だ果たせぬ決着への無念」が彼を動かしていることが示唆されましたw.atwiki.jp。それを知ったサイ・サイシーはもはや逃げず、祖父に代わってダハールと真正面から拳を交える決意を固めますw.atwiki.jp。
激戦の末、サイ・サイシーはドラゴンガンダムの必殺奥義「宝華教典・十絶陣」を発動。祖父ゆかりのフェイロンフラッグ(飛竜刀)で繰り出す火炎陣によってファラオガンダムIV世を焼き尽くし、ついに亡霊ファイターを撃破しましたgundam.wiki.cre.jpedgecute.livedoor.blog。長き因縁に終止符が打たれ、ダハールの魂もこれで眠りにつける……かに思われました。ところが次の瞬間、真っ黒に炭化したはずの機体がうごめき始めます。剥き出しの機体フレームに異形の再生が起こり、見る間にファラオガンダムIV世が完全復活してしまったのですw.atwiki.jp! もはやそれは人知の技を超えた「悪魔そのもの」であり、恨みを晴らして成仏できるはずのダハールの亡骸すらデビルガンダムの細胞によって強制的に蘇生・利用されている恐怖の光景でしたedgecute.livedoor.blog。
「お前はもう手を出すな!! シャァァイニング!! フィンガァァァーーッ!!!」w.atwiki.jp突如割って入ったドモンのシャイニングガンダムが渾身のシャイニングフィンガーを炸裂させ、悪魔と化したファラオガンダムの頭部を粉砕しますw.atwiki.jp。なおも再生しようと蠢く亡霊ガンダムに対し、ドモンは怒りとともにハイパーモードを発動。黄金のオーラを纏ったシャイニングガンダムのシャイニングフィンガーソードでファラオガンダムIV世を粉々に切り裂き、再起不能にしましたw.atwiki.jp。ドモンは舞い散る機体の残骸を見届けると、ダハールの干からびた亡骸をそっと掴み取り、その魂を弔うかのように砂に還しましたw.atwiki.jp。
戦いが終わり、辺りには静寂が戻ります。亡霊ファイターの暴走は収束しましたが、ドモンの胸には怒りと悲しみが残りました。デビルガンダムの放ったDG細胞が、死者の未練さえも利用して人を怪物に変えてしまうという事実に気づいたからです。「純粋にファイトを望む心さえも、DG細胞に侵され利用される」とドモンは憤り、ファイターの尊厳を踏みにじる悪魔の所業に改めて怒りを燃やしますedgecute.livedoor.blog。同時に、今回の事件が自ら追い求めている“宿敵”=デビルガンダムに繋がる初めての手掛かりであることも確信しましたedgecute.livedoor.blog。砂漠に消えゆくダハールの魂を見送りつつ、ドモンたちは次なる戦いへと旅立っていきます。
2. 登場キャラクター
- ドモン・カッシュ – 本作の主人公でネオジャパン代表ガンダムファイター。流派東方不敗の拳法使い。第10話ではサイ・サイシーと行動を共にし、亡霊ファイター事件に直面します。超常現象には動じないタフさを見せつつ、仲間を守るため果敢に立ち向かいました。物語終盤ではデビルガンダムへの手掛かりを掴み、戦士としての決意を新たにしていますedgecute.livedoor.blog。
- サイ・サイシー – ネオチャイナ代表の16歳の少年ファイター。祖父サイ・フェイロン譲りの拳法とドラゴンガンダムを駆り健闘中です。第3話でドモンに敗れて以降は良き友人となり、第10話で再登場しましたedgecute.livedoor.blog。普段は陽気で生意気な彼もオバケは大の苦手で、亡霊ファイターに終始ビクビクedgecute.livedoor.blog。しかし祖父の仇でもあるダハールの無念を知ると一転、恐怖を克服し正々堂々ガンダムファイトで応じる熱い一面を見せましたw.atwiki.jp。今回の戦いで精神的にも大きく成長したと言えます。
- レイン・ミカムラ – ドモンの幼なじみにしてパートナーである天才メカニック兼ドクター。ネオジャパンチームのメンバーとしてドモンをサポートします。第10話では持ち前の機転で手榴弾を用意しており、亡霊に襲われたサイ・サイシーを救う決定打となりましたedgecute.livedoor.blog。「レイン、アレを使え!」に即応する姿からも分かる通り、常に非常時に備えている有能さが光ります。女性ながら度胸も据わっており、ホラー展開でも冷静に状況分析を行っていました。
- ダハール・ムハマンド – かつて未来世紀20年(第3回ガンダムファイト)で優勝を果たした伝説の英雄gundam.wiki.cre.jpg-gundam.net。ネオエジプト代表としてファラオガンダムIII世を駆り栄冠を手にした後、第4回大会にも連覇を懸けて出場しましたg-gundam.net。しかし決勝戦でネオチャイナ代表サイ・フェイロン(=サイ・サイシーの祖父)のフェイロンガンダムに敗北し、機体の爆発に巻き込まれて非業の死を遂げますg-gundam.netdic.pixiv.net。ネオエジプトには彼の偉業を称えて専用のピラミッド型墓所が建造され、愛機ファラオガンダムIV世と共に安置されましたgundam.wiki.cre.jpgundam.wiki.cre.jp。――それから36年後、デビルガンダムのDG細胞によって死体のまま蘇生され、第10話の「亡霊ファイター」となってしまいますgundam.wiki.cre.jpgundam.wiki.cre.jp。劇中では台詞らしい台詞を発することはなく唸り声程度ですが、設定上は声優・笹岡繁蔵氏がCVを担当しました。生前は誇り高き武闘家でしたが、DG細胞に侵された復活後は自我を失ったゾンビ同然となり、生前の記憶であるサイ・フェイロンへの闘志だけを頼りに動いていたのが悲劇ですw.atwiki.jp。最期はドモンによって完全に解放され、その魂は安らぎを取り戻しました。
- サイ・フェイロン – 故人。サイ・サイシーの祖父であり、ネオチャイナの英雄的存在。第4回ガンダムファイト優勝者で、搭乗機はフェイロンガンダムですw.atwiki.jp。決勝戦でダハールのファラオガンダムIV世を破った張本人ですが、その際ダハールを事故死させてしまったことがサイ・フェイロンにとっても心残りだったようです(アニメ本編では故人のため登場しませんが、第10話で写真や回想にて存在が語られます)。サイ・サイシーは幼い頃に祖父から武術の手解きを受けており、フェイロンガンダムの操縦術や必殺技も受け継いでいます。亡霊ファイターとの決戦では、サイ・サイシーが祖父の形見である「フェイロンフラッグ」(流派・宝竜[ほうりゅう]刀)を手に戦いましたedgecute.livedoor.blog。孫の戦いぶりはきっと天国で見守っていたことでしょう。
- カウラー・ラムゼス – 第13回大会におけるネオエジプト代表ファイター。ファラオガンダムXIII世のパイロットですが、第10話冒頭でダハールの亡霊に奇襲され命を落としますdic.pixiv.netdic.pixiv.net。劇中では直接名前は呼ばれませんが、設定上は古代エジプト風の名前「カウラー・ラムゼス」という人物ですdic.pixiv.net。ファラオガンダムXIII世が「一般兵士モチーフ」の機体であることから、ラムゼスも民衆階級出身のファイターだったと推測されます。せっかく予選を勝ち抜いたものの、ファラオガンダムXIII世諸共亡霊に葬られ、本戦に姿を見せることは叶いませんでしたdic.pixiv.net。彼とクルーたちの最期の言葉「ダハール…」が今回の事件の謎を解くヒントとなり、レインがその手掛かりを分析していますdatenoba.exblog.jpja.wikipedia.org。
3. 登場モビルファイター
第10話に登場するファラオガンダムIV世(右)とドラゴンガンダム(左)。ファラオガンダムIV世は古代エジプト王族を思わせる黄金のマスクと細身のシルエットが特徴だが、亡霊として復活した際には全身に包帯が巻かれミイラのような不気味な姿で出現したgundam.wiki.cre.jpgundam.wiki.cre.jp。ドラゴンガンダム(フェイロンガンダムに似た姿)を見て闘志を掻き立てている。
- ファラオガンダムIV世 – ネオエジプトが第4回ガンダムファイト(未来世紀16年)用に開発したモビルファイターgundam.wiki.cre.jp。デザインモチーフは古代エジプトのファラオ(王族)であり、頭部にはツタンカーメン風のマスクを思わせる黄金の装飾、顎には長い髭飾りのようなパーツが特徴ですw.atwiki.jp。ボディカラーは砂漠に馴染む淡い亜麻色で、がっしりとした体躯をしていますw.atwiki.jp。形式番号はGF4-001NE。第3回大会優勝機ファラオガンダムIII世を改修して作られた後継機で、搭乗者は英雄ダハール・ムハマンドでしたgundam.wiki.cre.jp。しかし第4回大会決勝でネオチャイナのフェイロンガンダムに首をはねられて敗北し、機体もろとも爆発四散、ダハールも戦死しますw.atwiki.jp。そのためファラオガンダムIV世とダハールの遺体はネオエジプトに建造されたピラミッド型の墓所に共に埋葬されましたgundam.wiki.cre.jpgundam.wiki.cre.jp。 物語本編では、第10話で亡霊ファイターとして登場。デビルガンダムのDG細胞によって機体ごと蘇生・稼働しており、全身にぐるぐる巻きの包帯を纏った不気味な姿で出現しましたgundam.wiki.cre.jp。生前の淡いカラーリングは覆い隠され、包帯の下から覗く目は怪しく紅く発光していますedgecute.livedoor.blog。またDG細胞の力により高い自己再生能力を獲得しており、一度破壊されても瞬く間に完全再生してしまいますg-gundam.netgundam.wiki.cre.jp。この驚異的な回復力の前にサイ・サイシーは苦戦を強いられました。さらに、亡霊状態のダハールは幽霊らしく隠密性も発揮しており、砂嵐の夜に現れては姿を消すなど神出鬼没でしたgundam.wiki.cre.jp。劇中冒頭ではネオエジプトのキャンプを奇襲し、最新鋭の後継機ファラオガンダムXIII世を破壊、クルーを皆殺しにしているなど残忍な一面も見せていますgundam.wiki.cre.jp。 武装・特殊能力としては、生前からの固定装備である頭部バルカン砲(ツインアイ脇に2門内蔵)やマンバ・ウィップ(両腕に内蔵された蛇頭状の鞭)を使用しますgundam.wiki.cre.jp。ただしテレビ本編でこれらの通常武装がクローズアップされる場面はありません。むしろDG細胞汚染後に獲得した異質な武器として、包帯そのものを自在に伸縮・操作して敵を絡め取る包帯攻撃や、包帯に電流を流す攻撃を披露しましたgundam.wiki.cre.jp。さらにミイラ男の眼から放つ怪光線(ビーム)gundam.wiki.cre.jp、胸部から発射する高出力のビーム砲(スペック外のためDG細胞由来とも言われる)など、多彩かつ怪奇な攻撃を見せていますgundam.wiki.cre.jp。周囲に砂嵐を発生させて姿を眩ます能力も確認されており、これら人智を超えた戦法はデビルガンダム細胞の恐ろしさを物語っていますgundam.wiki.cre.jp。最期はドモンのシャイニングフィンガーソードで粉砕され、完全消滅しましたw.atwiki.jp。
- ファラオガンダムXIII世 – 第13回ガンダムファイト(本編の大会)におけるネオエジプト代表MF。形式番号GF13-051NE。全高16.6m、重量7.8tと歴代ファラオガンダムと同スペックですdic.pixiv.net。機体名が示す通りネオエジプトは**代々「ファラオガンダム○世」の名を継承して大会に挑んでおり、本機も13代目にあたりますdic.pixiv.net。ただし過去のファラオガンダムIII世やIV世が「古代エジプト王朝の王族(ファラオ)」をモチーフとしていたのに対し、ファラオガンダムXIII世のデザインモチーフは「古代エジプトの一般兵士」**となっていますdic.pixiv.netdic.pixiv.net。具体的には頭部に王冠ではなく兵士風の簡素な兜飾りを頂き、全身も白い布地を巻き付けた軽装歩兵のような出で立ちです(実際カラーリングは白地に青のラインが基調で、パイロットスーツも白地に胸元へウジャト眼のマークが描かれ兵士風になっていましたdic.pixiv.net)。兵士モチーフだけあって装備はシンプルで、頭部バルカン砲の他に何らかの武装があったようですが、本編で活躍シーンが無かったため詳細不明ですdic.pixiv.net。性能面では歴代のファラオガンダム譲りで砂漠戦を得意としており、機動性・戦闘力とも高かったと思われますdic.pixiv.net。 パイロットはカウラー・ラムゼス。しかし彼とファラオガンダムXIII世は、第10話の開幕早々にダハールの亡霊による奇襲を受けてしまいます。整備中の不意打ちでコックピットを一撃破壊され、ラムゼス以下クルーもろとも爆殺されてしまいましたdic.pixiv.net。さらに機体の残骸は亡霊ファラオガンダムIV世に「部品取り」として利用されてしまったため、ネオエジプトは予選敗退扱いとなりますdic.pixiv.net。劇中では動いている場面すらなく一瞬で退場する不遇な最新鋭機ですが、第13回大会参加MFとして名前だけは公式資料に残っています(海外版での名称は「Mummy Gundam XIII」)dic.pixiv.net。ファンからは「ある意味もっとも悲惨な敗退を遂げたガンダムファイター」とも言われますが、それだけ亡霊ダハールの怨念が凄まじかった証と言えるでしょう。
- ドラゴンガンダム – ネオチャイナ代表MF。操縦者はサイ・サイシー。中国拳法の使い手らしく近接格闘戦を主体とする機体で、両腕を伸縮自在な竜の腕(ドラゴンクロー)に変形させることができます。第10話ではたまたまネオエジプトを訪れていたところ亡霊ファイターに狙われ、標的となってしまいましたgundam.wiki.cre.jp。というのも、ドラゴンガンダムの外観がかつてダハールを破ったフェイロンガンダムに酷似していたため、ダハールの亡霊はドラゴンガンダムを宿敵フェイロンガンダムと誤認したのですgundam.wiki.cre.jp。劇中序盤、サイ・サイシーは挑発に乗って亡霊のファラオガンダムIV世と一騎打ちになりますが、激闘の末に禁じ手のコックピット攻撃で辛勝しますedgecute.livedoor.blog(このことで彼はルール違反の罪悪感に苛まれ、後の戦いで消極的になっていましたedgecute.livedoor.blog)。しかし復活した亡霊との再戦では、その「生前の無念」を知って逃げずに戦うことを決意。秘策として亡き祖父から受け継いだ**宝竜刀(フェイロンフラッグ)**を駆使した必殺奥義「宝華教典・十絶陣」で亡霊を撃破しましたgundam.wiki.cre.jp。通常の格闘戦のみならず、こうした火炎を用いた広範囲攻撃も繰り出せるのがドラゴンガンダムの強みです。結果的にドラゴンガンダムは亡霊ファイターに2戦2勝した形ですが、いずれもDG細胞による規格外の再生能力に翻弄され、最後はドモンの助太刀を受けています。この一連の戦いを経て、サイ・サイシーとドラゴンガンダムは精神面で大きく成長することになりました。
- シャイニングガンダム – ネオジャパン代表MF。操縦者はドモン・カッシュ。東方不敗の流派に伝わるキング・オブ・ハートの紋章を胸に刻む機体です。第10話では本来戦いに介入する立場ではありませんでしたが、デビルガンダムの魔手が絡んだ異常事態を前に最後の止めを刺すべく乱入しましたw.atwiki.jp。クライマックスではドモンの怒りに呼応して**ハイパーモード(金色に輝くスーパーモード)**を発動し、DG細胞の悪鬼と化したファラオガンダムIV世を「シャイニングフィンガーソード」で一刀両断にしていますw.atwiki.jp。シャイニングガンダム自体の活躍は一瞬でしたが、デビルガンダム事件への強い手掛かりを掴んだ重要なシーンでした。なお、亡霊ファイター出現時のドモンはあくまで非戦闘中だったため、モビルトレースシステム用の戦闘スーツは着用せず普段着のままシャイニングに搭乗しています(それでも的確に機体を操縦できるのはさすがですね)。
- スフィンクスガンダム – ネオエジプトのもう一つのガンダム。こちらは第10話では登場しませんが、物語終盤の第48話「地球SOS!出撃ガンダム連合!!」にワンシーンだけ姿を見せますdic.pixiv.net。ネオエジプトコロニー内に鎮座する巨大なスフィンクス石像が変形し、その内部から出現した機体ですdic.pixiv.net。その姿は**「ガンダムの顔を持つ獅子(スフィンクス)」という異形のフォルムで、四足歩行の超巨大ガンダムになっていますdic.pixiv.net。操縦者や具体的な武装・戦闘描写は一切不明で、おそらくネオエジプトコロニーの最終防衛用兵器として登場したものと考えられますdic.pixiv.net。その巨体と非人間型の形状から、厳密にはガンダムファイト用のモビルファイターではなくモビルアーマーに近い存在と思われますdic.pixiv.net。劇中ではデビルガンダムの地球侵攻に対抗する各国連合軍の一機として発進する場面のみ確認できますdic.pixiv.net。ファラオガンダムシリーズとは直接関係ありませんが、同じネオエジプトの機体として古代エジプト神話の怪物スフィンクス**をモチーフにデザインされている点が興味深いですdic.pixiv.net。四足獣タイプのガンダムという珍しさもあり、放映当時ファンの間で話題になりました。なおスフィンクスガンダムは劇中での活躍こそ皆無でしたが、SDガンダムの漫画『黄金神話』では怪物キャラとして登場したことがありますdic.pixiv.net。
4. 技・演出
第10話「恐怖!亡霊ファイター出現」は、ホラー映画さながらの演出とスピーディーな対決シーンが光るエピソードです。冒頭、砂漠のキャンプで怪談話に花を咲かせるクルーたちのシーンから物語は始まりますedgecute.livedoor.blog。ピラミッドやミイラ男といったエジプトの定番ホラー要素がテンポよく盛り込まれ、夜の赤い月や不気味な肖像画など演出面でも雰囲気たっぷりですedgecute.livedoor.blogedgecute.livedoor.blog。サイ・サイシーが怖がって夜中にトイレに行くと幽霊と遭遇する……といったホラーの「お約束」もきっちり押さえられており、視聴者に程よい緊張感とコミカルな笑いを提供していますedgecute.livedoor.blog。一方で、墓所での襲撃シーンでは肖像画の目が光って亡霊が飛び出すというベタな恐怖演出に「なぜそこから出てくる!?」とツッコミを入れたくなるコミカルさもあり、シリアスとユーモアのバランスが巧みですedgecute.livedoor.blog。このように本エピソードはホラーテイストを織り交ぜつつもエンターテインメント性が高く、懐の深いGガンダムの世界観を感じさせます。
戦闘シーンの演出も見どころ満載です。特にクライマックスのドラゴンガンダムVSファラオガンダムIV世(亡霊)第2ラウンドは、サイ・サイシーの恐怖克服とともに映像に熱量が加わっていきます。サイが「ガンダムファイト、レディー・ゴーッ!」と渾身のファイトコールを上げるシーンでは、背景に炎が燃え盛るような演出で彼の闘志が強調されました。亡霊ファイター側も低い唸り声で応じ、一瞬だけ戦士の魂が共鳴するような演出がニクいところです。また、サイ・サイシーが繰り出す必殺技「宝華教典・十絶陣」のカッコ良さは特筆ものでしょう。祖父譲りの宝竜刀を手に、無数の火柱で敵を囲むその様は、まさに円陣焼殺陣。漢字のエフェクトが宙を舞うなど、中国拳法の奥義らしい派手な演出で描かれました。劇中では具体的な技名コールはありませんが、視覚的に「十絶陣」を表現することで視聴者にも直感的なインパクトを与えています。
ドモンの乱入からラストへの流れも熱く盛り上がります。亡霊ガンダムが再生し絶望感が漂う中、「お前はもう手を出すな!」と叫んでシャイニングガンダムが颯爽と登場するシーンでは、BGMも一気に主人公モードへ切り替わり鳥肌ものです。ドモンの怒りとともにシャイニングフィンガーが炸裂し、さらにスーパーモード発動からのシャイニングフィンガーソードへ繋げる演出は爽快感抜群でした。頭部を掴み潰されてもなお再生しようとするファラオガンダムIV世に対し、金色に輝くシャイニングガンダムが連撃で粉砕する様子は、まさに「悪を断つ光」という図式で描かれています。破片が砂となって消えていく演出も相まって、一連の決着シーンはシリーズ屈指の名アクションと言えるでしょう。
細かな演出面では、レインが手榴弾を使用する意外性も面白いポイントです。ガンダムファイトの真っ最中に生身の人間が武器を使うのは異例ですが、今回は相手が幽霊というイレギュラーな状況のためか、思い切った演出が取り入れられました(しかも墓所全体を崩壊させる程の威力で、ギャグ的なケレン味も感じさせますedgecute.livedoor.blog)。また、サイ・サイシーが戦いの最中に亡霊の真意を聞かされて心境が変化する場面では、過去のフェイロンガンダムVSファラオガンダムIV世のモノクロ回想がインサートされ、因縁が視覚的に語られました。祖父の残像と重なるようにサイが奮起する演出は感動的です。
総じて第10話の演出は、「ホラー+バトル+人間ドラマ」の融合が巧みに図られています。監督の今川泰宏氏は自身の過去作『ジャイアントロボ』での怪奇描写を想起させつつ、ミイラ男ガンダムという斬新な題材を大胆に映像化しました。今川監督は当初「ファラオガンダムIV世がジャイアントロボに似てると言われないか苦労した」そうですがdic.pixiv.net、結果的にはGガンダムならではの痛快な仕上がりとなっています。恐怖演出の中にも熱血とギャグを忘れない、本作らしいエンターテインメント精神が光る回でした。
5. 名シーン・名セリフ
「よおおおおおし! ガンダムファイトォ…レディィ!! ゴォーーッ!!!」
亡霊ファイターとの再戦を前に、サイ・サイシーが放った渾身のガンダムファイト宣言。幽霊相手にも正式な試合として立ち向かう姿勢を示した、彼の成長を象徴するセリフです。最初はオバケ怖さに泣き言を言っていたサイが、一転してこの名台詞を叫ぶ様子には思わず胸が熱くなります。劇中ではサイの絶叫に呼応するかのように亡霊ダハールも雄叫びを上げ、一瞬のうちに戦いの空気がピーンと張り詰めました。ファイター同士の魂が通じ合ったようなこの瞬間は、多くのファンの記憶に残る名シーンです。
「お前はもう手を出すな!! シャァァイニング!! フィンガァァァーーッ!!!」w.atwiki.jp
ドモン・カッシュの必殺の掛け声。再生怪人のごとく甦ったファラオガンダムIV世に対し、怒れるドモンが放った決め台詞です。シャイニングガンダムが登場するや否やこの叫びを挙げるシーンは、第1話の「俺のこの手が真っ赤に燃える!」に匹敵する爽快さがあります。普段は冷静沈着なドモンが明らかに怒りを滲ませ、「シャイニングフィンガー!!」ではなく敢えて「シャイニングフィンガーーッ!!!」と長く引っ張って叫ぶ様子から、彼の激昂ぶりが伝わってきます。その直後に頭部を握り潰し、さらにフィンガーソードで粉砕する一連の流れも含め、視聴者に強烈な印象を残しました。「もう手を出すな!!」というセリフは傍で見守るサイ・サイシーへの思いやりも感じさせ、ドモンの熱い人間性が垣間見える名セリフでもあります。
「純粋にファイトを望む心さえも、DG細胞に侵され利用される…」
明確な台詞として劇中にあるわけではありませんが、第10話のテーマを象徴する言葉としてドモン(あるいはナレーション)が述懐したように演出された一節ですedgecute.livedoor.blog。亡霊ファイター=ダハールの悲劇を目の当たりにしたドモンが、デビルガンダムの非道さに憤るシーンで語られました。戦士としての純粋な執念さえも踏みにじり悪用するDG細胞の恐怖が端的に表現されており、聞いていてゾッとする印象深いセリフです。この言葉によって物語全体の悪役であるデビルガンダムの脅威が改めて強調され、同時にダハールという男の無念さも胸に迫ってきます。ドモンの静かな怒りが伝わる名場面でした。
「レイン、アレを使え!」
ドモンがレインにかけた一言。ホラー一色だった墓所のシーンで、このセリフから一気に痛快なアクション展開へと転じました。レインが満を持して取り出した「アレ」の正体はまさかの手榴弾edgecute.livedoor.blog。ガンダムファイト中に生身の女性が爆弾を投げるという異例のシチュエーションに、多くの視聴者が驚いたことでしょう。結果的にこの判断がサイ・サイシーを救うことになり、「持つべきものは優秀なパートナー」と感じさせる小気味よい名シーンでした。レインの頼もしさと、ドモンとの抜群のコンビネーションを示すセリフとして挙げられます。
他にも、亡霊ダハールが墓所に現れるシーンでの不気味な呻き声や、サイ・サイシーの情けない悲鳴(「ひぃ~!」と情けなく取り乱す様子)はコミカルな名場面として語られることがあります。さらにはエンディング直前、ドモンが静かにダハールの遺骸を砕いて埋葬する無言のシーンも印象的です。セリフは無いものの、ドモンの心中を思いやると胸に迫るものがあります。このように第10話はセリフ・シーンともにバラエティ豊かで、笑いあり涙ありの名場面が詰まった回となっています。
6. 裏話・制作トリビア
- 名称の由来と海外版:ネオエジプトのガンダムは、伝統的に**「ファラオガンダム○世」という名で大会に参加する設定になっていますdic.pixiv.net。第1回から毎回ファラオガンダムを出しており、第3回でようやく優勝を勝ち取ったという歴史が語られていますw.atwiki.jp。ちなみに第13回大会用のファラオガンダムXIII世は他の「○世」達とモチーフが異なり、「古代エジプトの兵士」がモデルですdic.pixiv.net(劇中で活躍できなかったため目立ちませんが…)。余談ですが、海外英語版では「Pharaoh Gundam」は差別的なイメージを避けるためか「Mummy Gundam(マミーガンダム)」**と改名されていますdic.pixiv.net。確かに包帯グルグルの見た目からして“Mummy”そのものなので、的確なネーミングと言えるでしょう。
- デザインと今川監督の苦労話:ファラオガンダムIV世のデザインは大河原邦男氏によるものですgundam.wiki.cre.jp。古代エジプト風の意匠が凝らされていますが、その仕上がりについて今川泰宏監督は少々気を揉んだそうです。徳間書店刊『ロマンアルバム・テクニカルマニュアル奥義大全』によれば、「ファラオガンダムIV世が**『ジャイアントロボ』に似てると言われないよう苦労した」旨を今川監督が語っていたとかdic.pixiv.net。確かに言われてみれば、ジャイアントロボ(今川監督の前作アニメ)にも包帯姿のロボット怪人が登場しており、図らずもモチーフが被ってしまった部分があったようです。もっとも実際の映像ではGガンダム流の派手なキャラクター性が加味され、オリジナリティあふれる「ミイラ怪人ガンダム」として成立していました。監督の杞憂を吹き飛ばすほど強烈なインパクトがあったと言えるでしょう。
- ホラー回となった経緯:なぜガンダム作品で幽霊・ミイラ男?と意外に思う方もいるかもしれません。本作は国ごとの特色をガンダムに反映するコンセプトがあり、エジプトと言えばピラミッドとミイラという誰もが連想する題材を盛り込んだ結果、第10話がホラー調の物語になりましたedgecute.livedoor.blog。シナリオ担当の五武冬史氏と今川監督は、「Gガンダムは何でもあり」の方針で様々なジャンルのエッセンスを取り入れており、宇宙刑事もの(第8話)や銃撃戦スパイもの(第9話)など毎回趣向を変えています。第10話はその一環でホラー冒険活劇となりましたが、実は物語の本筋(デビルガンダム編)への伏線も兼ねている重要回です。幽霊ファイターというインパクト重視のアイデアを採用しつつ、デビルガンダムの能力(DG細胞による死者復活)をここで初披露することで物語を大きく動かしています。エンタメ性とストーリー進行を両立させた巧みな構成と言えるでしょう。
- コミックボンボン版での違い:今作には当時、講談社の『コミックボンボン』で連載された漫画版(作画:ときた洸一氏)があります。漫画版ではアニメ第10話に相当するエピソードが少し異なる展開で描かれました。舞台はパリで、ダハールのファラオガンダムIV世がガンダムローズ(ジョルジュ・ド・サンドの機体)と交戦してあえなく敗北する場面から始まりますdic.pixiv.net。その後、ドモンVSジョルジュ戦の直後にDG細胞が暴走し、テレビ版以上に凄まじいミイラ怪人の姿となってシャイニングガンダムに襲いかかりましたdic.pixiv.net。途中経過は尺の都合で省略されたものの、最終的にはドモンとジョルジュの共闘で完全に撃破され、ダハールはデビルガンダムの犠牲となったことが悼まれましたdic.pixiv.net。漫画版ではアレンジとしてジョルジュ(ネオフランス代表)が関与し、本編以上にホラー描写がグロテスクだった点が興味深いです。また、漫画版オリジナル要素としてガンダムヘッド(デビルガンダムの刺客メカ)がダハールをDG細胞で復活させるシーンが描かれ、デビルガンダムの暗躍がより直接的に示唆されています。媒体の違いによるストーリー展開の差異も、ファンには楽しめるトリビアでしょう。
- 玩具展開と関連商品:ファラオガンダムIV世はその独特なデザインから玩具的な人気もありました。放映当時、バンダイの可動フィギュアシリーズ「MIA(モビルスーツ・イン・アクション)」でファラオガンダムIV世が商品化されています。国内版では次回登場のミナレットガンダム(ネオトルコ代表)とのセット販売でしたがgunplapocchi.com、海外版では単品発売されました(海外名称が“Mummy Gundam IV”ゆえか、レアアイテム化していますgunplapocchi.com)。フィギュアではマンバ・ウィップ(蛇型ムチ)も再現されており、劇中さながらのポージングが可能ですgunplapocchi.com。「GガンのMIAの中でこいつ(ファラオガンダムIV世)は特にお気に入り」とレビューで語られるほどgunplapocchi.com、ファンからも愛されている機体です。また2022年には今川監督監修の公式外伝コミック『機動武闘伝Gガンダム外伝 暗黒のデスファイト』が刊行され、デビルガンダム四天王やDG細胞絡みの設定が補完されました。ファラオガンダムIV世直撃のエピソードはないものの、第10話で撒かれたDG細胞復活のアイデアはその後の作品にも影響を与えていると言えるでしょう。
7. 解説・考察
● なぜ「ファラオガンダム」が採用されたのか?
ネオエジプトという舞台でガンダムファイトを描くにあたり、製作陣は「エジプトらしさ」をとことん追求しました。その結果生まれたのが「ファラオガンダム」シリーズです。ガンダムファイトの各国機体は国民的アイコンのオマージュであり、エジプトの象徴であるファラオ(及びミイラ)がモチーフになるのは必然とも言えます。第10話はホラー仕立ての異色回ですが、実は亡霊ファイター=ミイラ男という図式はエジプト編として分かりやすく視聴者に訴求する狙いがありましたedgecute.livedoor.blog。怪談やピラミッド探検のワクワク感で物語に引き込みつつ、デビルガンダムの恐怖も描くという一石二鳥の脚本です。さらに、主人公ドモンだけでなく仲間のサイ・サイシーにもスポットを当て、キャラクターの掘り下げ(サイの成長と祖父の因縁)を行っている点も評価できます。ファラオガンダムIV世は、その「亡霊」「因縁」「エジプト」「DG細胞」という複数のテーマの交点に位置する存在でした。おそらく企画段階からネオエジプト編はこの路線で行こうと決められていたのでしょう。結果として強烈な個性を放つ回になり、放送から年月を経た今でも「ミイラガンダムの話」としてファンに語り継がれるエピソードとなりました。
● DG細胞に浸食されたファイターの世代
第10話で初めて明かされたのは、デビルガンダムのDG細胞には死者さえ蘇らせる驚異の力があるということでしたw.atwiki.jp。ダハール・ムハマンドという往年のチャンピオン(第4回大会出場者)をゾンビ化してしまうDG細胞の設定は、その後のストーリーにも大きく影響します。例えば第33話「地獄からの使者!チャップマン復活」では、ネオイングランドの元ガンダムファイターで英雄だったジェントル・チャップマンが死後DG細胞で復活し、デビルガンダム四天王の一角として襲来しますsrw.wiki.cre.jp。チャップマンはかつて第9~11回大会で三連覇を果たした伝説の射撃手でしたが、第9話で描かれたように老いや薬物中毒で引退に追い込まれていました。それがDG細胞により亡霊さながら蘇生・強化され、「かつての全盛期以上の強さ」を得てドモンたちの前に立ちはだかります(劇中でマスター・アジアが「チャップマンは三連覇時以上の強さを得ておる」と語る場面があります)datenoba.exblog.jp。このようにデビルガンダムは歴代ファイター(しかも英雄級のレジェンド)を次々と蘇らせて手駒にしているのです。世代的には、第4回大会のダハール、第9~11回大会のチャップマン、そして第12回大会優勝者でドモンの師匠東方不敗マスター・アジアもデビルガンダム側につきました。マスター・アジアの場合は生存したまま協力者となった特殊ケースですが、その身体は後にDG細胞に侵されていきます。いずれにせよ、過去の名ファイター達の世代がデビルガンダムの力で怪物化・傀儡化していく展開は、本作の終盤に向けた盛り上がりの一要因となりました。あたかも**「過去の栄光」がDG細胞によって穢される**かのような描写は、ヒーロー像の多様性を描くGガンダムならではのアプローチと言えますdatenoba.exblog.jp。ダハールは最期に救われましたが、チャップマンは完全に悪に墜ちてしまうなど、それぞれの末路にも明暗が生まれています。
● マスター・アジアやウォンの暗躍との関係
第10話時点では明かされていませんが、亡霊ファイター事件の裏ではネオホンコン首脳であるウォン・ユンファ(第13回大会主催者)や、東方不敗マスター・アジアの思惑も絡んでいた可能性があります。後のエピソードで判明するように、ウォンはデビルガンダムの力を利用してガンダムファイトを牛耳ろうと画策しており、マスター・アジアもまたデビルガンダムを利用して人類粛清を目論んでいました。チャップマンをDG細胞に感染させ復活させたのがウォンの指示だったようにgundam-c.com、ダハールの蘇生もデビルガンダムの無計画な暴走ではなく、何者かの意図が働いていた可能性があります。マスター・アジアは決勝大会でドモンと相対した際、「DG細胞で蘇ったチャップマンは往年以上の強さ」と得意げに語っており、過去の英雄を蘇らせる行為に一定の理解(あるいは肯定)を示していました。もしかすると、マスター・アジアは亡霊ダハールの存在もどこかで把握していたのかもしれません。実際、第12話でマスター・アジアはデビルガンダムと共に姿を現し、ドモンに衝撃を与えます。そう考えると、第10話から既に**「師匠の影」は忍び寄っていたとも解釈できます。もっとも真相は劇中で明言されていないため、あくまで想像の域を出ません。ただ、デビルガンダムのDG細胞が暴走するきっかけには必ず人為的な目的が絡んでおり、亡霊ファイターの出現も結果的にドモンたちをデビルガンダムの存在へ導くための誘導策**になったのは確かですedgecute.livedoor.blog。マスター・アジアは自らの弟子であるドモンを試練にかける節がある人物ゆえ、この亡霊事件も「ドモンを鍛えるための踏み台」として静観していたのかもしれません。いずれにせよ、第10話は謎の亡霊という怪奇現象を通して、背後に潜む黒幕(デビルガンダム陣営)の存在を観客に示唆する重要なターニングポイントとなりました。
● ファラオガンダムとスフィンクスガンダムの選定背景
ネオエジプトには他国に比べ2種類のガンダムが登場します。劇中メインで扱われた人型のファラオガンダムシリーズと、第48話で一瞬登場した四足獣型のスフィンクスガンダムです。この両者の違いと使い分けには興味深いものがあります。まずファラオガンダムは前述の通り歴代大会で使用されてきた正式なガンダムファイト用MFであり、人型で汎用性が高いのが特徴ですdic.pixiv.net。対してスフィンクスガンダムは、人型ガンダムの常識を逸脱した超巨大メカであり、おそらくコロニー防衛兵器として位置付けられていますdic.pixiv.net。劇中でもスフィンクスガンダムはガンダムファイトには参加しておらず、ネオエジプトコロニーが非常事態に陥った際の最終手段としてのみ起動していますdic.pixiv.net。つまり**「ガンダムファイト用」と「非常用兵器」で棲み分けがされているわけです。製作裏話的に推測すれば、当初からネオエジプトのモビルファイターはファラオ(王)とスフィンクス(獅子)という2案が存在し、どちらも捨て難かったため両方登場させてしまえ!という判断になったのではないでしょうか。結果、物語前半(第10話)ではファラオガンダムIV世をフィーチャーし、終盤(第48話)でサービス的にスフィンクスガンダムをカメオ出演させた形になっています。スフィンクスガンダムは非人間型であるため正式なファイトには不向きですが、その分インパクトは抜群で、終盤の盛り上がりに華を添えました。ファラオガンダムとスフィンクスガンダム、両者は「王」と「獣」というエジプトモチーフの二枚看板としてネオエジプトの存在感を高めるのに一役買っています。なお、スフィンクスガンダムに関しては資料が極端に少なく詳細不明な点も多いですが、ファラオガンダムXIII世とは用途も起源も異なるため単純な比較はできません。ただファンの間では「もしスフィンクスガンダムが本編で戦ったらどれほど強かったのか?」などと想像が語られることもあり、ある意味謎多きロマン枠**のMSとして愛されていますgundamlog.com。
● 亡霊ファイターの哀しき真実
考察として忘れてはならないのが、亡霊となったダハール・ムハマンドという男のドラマ性です。彼は生前、ネオエジプトを栄光に導いた英雄でありながら、不慮の死によって無念を残しましたw.atwiki.jp。その無念の想いがデビルガンダムに付け入られ、死して尚戦いを強いられるという運命はあまりに過酷です。ダハール本人の意思というよりは**「ファイターの魂」が半ば自動的にDG細胞に利用されて動いていた節もあり、もはや彼は自分の望みすらコントロールできない傀儡でしたw.atwiki.jp。サイ・サイシーとの再戦も、果たせなかったリベンジを果たしたい魂の叫びである一方、DG細胞に侵された身体は理性を失い相手を殺しかねない暴走を見せています。つまりダハールの物語は、「戦士の誇り」が「悪魔の技術」によって踏みにじられた悲劇と言えますw.atwiki.jp。最終的にシャイニングガンダムの手で破壊されたことで、ようやく彼の魂は解放されましたが、逆に言えばドモンが止めを刺してくれなければ永遠に地獄を彷徨うところでした。その意味で、第10話のラストでドモンがダハールの亡骸を握り潰して砂に還すシーンは、彼にとっての救済だったように思えますw.atwiki.jp。実際ドモンも無言のうちにその死を悼んでおり、ダハールの戦士としての尊厳を最後に守ったのでしょう。一方デビルガンダム側から見れば、ダハールを復活させたのは単なる実験や陽動作戦に過ぎなかったかもしれません。しかし皮肉にもこの事件がドモンに火を付け、彼がより一層デビルガンダム討伐に執念を燃やす結果となりましたedgecute.livedoor.blog。亡霊ファイター編は、単発のホラーエピソードであると同時にシリーズ全体の物語の転換点**であり、デビルガンダム編の本格化に舵を切る重要な役割を果たしているのです。
8. 筆者コメント(あとがき)
第10話「恐怖!亡霊ファイター出現」は、子供の頃にリアルタイム視聴していた筆者にとっても特に印象深いエピソードです。何しろ当時、小学生だった自分はテレビに映るミイラ男のガンダムに心底ビビったものです…。ガンダムシリーズで幽霊が出るなんて前代未聞で、「Gガンダムって本当に何でもアリなんだな!」と衝撃を受けた記憶があります。それでいて物語としてもしっかり面白く、ホラーにドキドキしつつ最後は熱いバトルでスカッとさせてくれる展開に大満足したのを覚えています。
改めて大人になって見直すと、亡霊ファイターことダハールの悲劇性に胸を打たれました。子供の頃は「怖い怪人が出てきた!」くらいの理解でしたが、今見ると戦士の無念と誇りというテーマがひしひしと伝わってきます。不本意ながら悪に利用されてしまったダハールが最後に救われる姿には、悪役ながら同情してしまいました。ドモンが黙って彼の亡骸を処理するシーンも渋い演出で、主役の優しさが垣間見えて好きです。サイ・サイシーも序盤との態度の落差が激しく、人間臭いキャラ描写が微笑ましいですね。廃墟でビクビク震えていた彼が、最終的に亡霊に立ち向かう姿にはこちらも応援したくなりました。まさに**「怖いけど熱い!」**Gガンダムならではの醍醐味を味わえる回だと思います。
演出的な観点では、当時のサンライズ制作スタッフの遊び心が随所に感じられました。例えば肖像画の目が光るシーンなんて古典的すぎて笑ってしまいますが、不思議と作品のノリに合っているんですよね。また、レインがちゃっかり手榴弾を持ち歩いてる設定も地味に好きなポイントです(笑)。彼女のおかげでサイ・サイシーは何度命を救われたことか…。サポートキャラの活躍が印象に残るのもこの回の良いところです。
そして忘れてならないのが、このエピソードがデビルガンダム編の本格スタートだったということ。後の展開を知った上で振り返ると、「ああ、ここでDG細胞のヤバさを示していたのか!」と合点がいきます。当時の自分は亡霊の正体がデビルガンダム絡みだとは分からず、ただ「怖い敵が出たなー」程度でした。しかし次の第11話以降でDG細胞感染者が続々登場し、「なるほど前回のミイラもそうだったのか!」と繋がる流れは見事でした。こうして見ると、Gガンダムは各話完結のように見えて実は伏線が緻密に張られているんですね。
総じて第10話はインパクト絶大な名エピソードです。ガンダムファイトというスポーツ大会ものにホラー要素を持ち込む大胆さ、その中でキャラを成長させストーリーを進展させる巧みさ。何度見ても楽しめる懐の深さがあります。未視聴の方には是非ご自身の目でこの“亡霊ファイター”の恐怖と感動を確かめてほしいですね。きっと「こんなガンダムもあったのか!」と驚くこと間違いなしです。
9. 次回予告
次回、第11話「雨の再会…フォーリング・レイン」。ネオトルコでドモンとレインを待つものは、かつての友との悲劇的な再会。デビルガンダムの魔手は新たなガンダムファイターにも及んでいた! 負傷し心に闇を抱えた男と、彼を救おうと奔走するレイン…。そして迫り来る黒い影にドモンは立ち向かう。雨の中、運命の歯車が再び動き出す! 次回もお楽しみに!

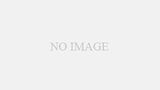
コメント